猫ちゃんの腎臓病のお話
【猫ちゃんの腎臓病・腎疾患】
本日は猫ちゃんの飼い主さまの多くが1度は聞いたことのある、猫ちゃんのかかりやすい病気『腎臓病』についてのお話です

猫ちゃんはもともと砂漠や高山など水の少ない場所に住んでいた動物で、少ない飲み水で効率よく生活がおくれるよう、尿を濃縮し濃い尿をする生き物です
しかし、腎臓の働きが良いあまり歳をとると共に腎臓に大きな負担がかかってしまいます
このため多くの高齢な猫ちゃんは腎臓の機能が低下し、また一度壊れてしまった腎臓は元に戻すことはできないため早期発見・早期治療が大切です!!
《腎臓とはどんな臓器?その働きは?》
そもそも腎臓とはどんな役割を持つ臓器なのかご存じでしょうか?
腎臓には大きく分けて4つの機能があります
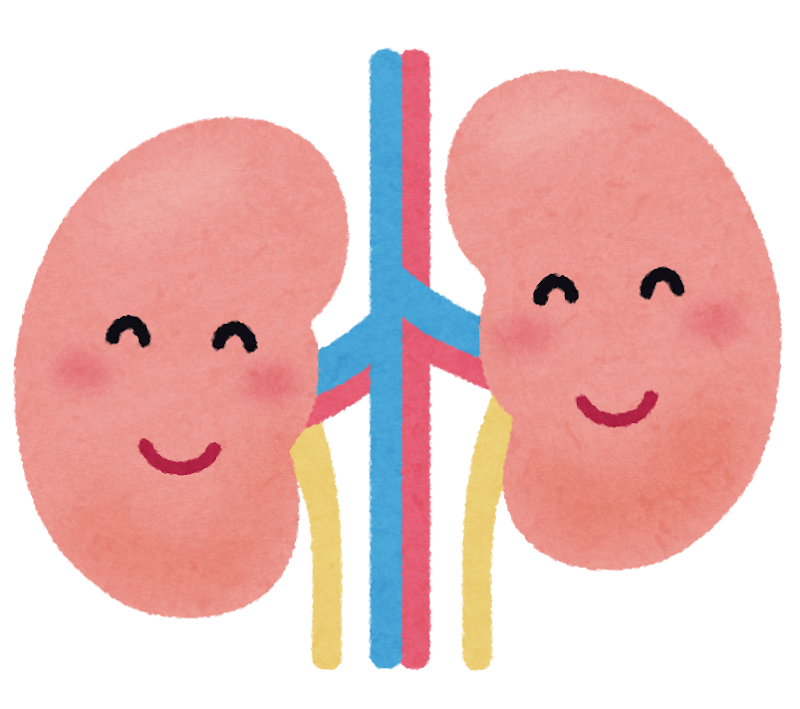
①水分の再吸収・尿の生成
摂取した水分を体調や気候に合わせて体の外に排出し、体の中の水分の量を調整しています
体中をめぐる血液は腎臓の中にある【ネフロン】という機能でろ過され、体に必要な水分は再び再吸収して体内に戻し、
不必要な水分や老廃物は“尿”として体の外に排出します
②老廃物の排泄
腎臓の機能である【ネフロン】は猫ちゃんでは約40万個ほど存在し、血液中の老廃物(毒素)をろ過し体の外に排出しています
③ミネラルバランスの調整
体にとって必要なカルシウム・リン・ナトリウムなどのミネラル成分の量を調整しています
④ホルモンの分泌
『エリスロポエチン』という血液中の赤血球を作る大切なホルモンを作っています
《腎臓病とはどんな病気なの?》
猫ちゃん全体では約10%、10歳以上の猫ちゃんでは30%~40%が罹患すると言われている腎臓病
猫ちゃんの死因でも上位に入るほど代表的な病気の1つです
健康な猫ちゃんでは体に溜まった不必要な老廃物を腎臓でろ過し尿として体の外に排泄することが出来ますが、【ネフロン】が壊れ腎臓の機能が低下すると
老廃物が上手く排泄することが出来ず体の中に溜まってしまいます
それでも体はその老廃物を何とか外に出そうとするため、濃縮しきれない薄い尿をたくさん出そうとします
その為体に必要な水分までが尿として排出されてしまうため体は脱水していきます
腎臓病の猫ちゃんの多くがお水をたくさん飲むようになるのはそのためです

また腎臓病が進行すると造血ホルモンが減少し、血液を作ることが出来なくなってしまうため末期になると体は貧血していきます
一度壊れてしまった腎臓の機能は元に戻すことはできず、徐々に進行していきます
《症状は?》
多くの飼い主さまが気が付かれる症状は以下の3つです
①多飲・多尿
「最近よくお水を飲む」・「以前よりもおしっこの回数・量が多い」・「お漏らしをするようになった」
※腎臓での尿の再吸収が上手くできずに体の外に出してしまうため、薄いおしっこをたくさんするようになり、お水をたくさん飲むようになります
②食欲不振・嘔吐
「最近なんだか食欲が落ちた」・「毛玉以外によく吐くようになった」・「気持ち悪そうに口をくちゃくちゃする」
※排泄されるべき毒素が体にたまり、吐き気が出たりよだれが多くなったりします
また気持ち悪さから食欲が落ちる子もいます

③元気消失
「最近元気がない」・「あまり動かなくなった」・「寝ている時間が多い」
※食欲の低下と共に貧血などの症状からあまり動きたがらなくなる子もいます
※また腎性高血圧といって腎臓の機能低下と共に血圧の上昇がみられることがあります

《診断方法は?どんな検査があるの?》
①尿検査
有効的な早期診断が可能な検査として尿検査があります
尿がしっかり濃縮できているのか、尿の中にタンパクが漏れ出ていないか、不純物が混ざっていないかを確認できます
※7歳を過ぎたころから年に1回尿検査を受けるなど、出来る限り早い段階で腎臓の異変を見つけることが大切です

②血液検査
血液検査で貧血のチェック、BUN(尿素窒素)・Cre(クレアチニン)・リンなどの数値を検査することで腎臓の機能を調べることが出来ます
またSDMAというさらに早期に腎臓の異常を発見することができる検査方法もあります
これは腎臓の【ネフロン】の一部である【糸球体のろ過率】を調べる検査であり、腎臓がどの程度障害を受けているのかを早期に調べることのできる検査方法です

③エコー検査やレントゲン検査
腎臓の形や大きさ、内部の構造などを画像で診断する検査です また腎臓内の結石の有無や腎臓の腫瘍を確認します
一般的には血液検査と一緒におこないます
《腎臓病の治療方法は?お薬はあるの?》
※いかに残された腎臓を守り、大事に長く使うかが重要!!
腎臓は一度壊れてしまうと、残念ながら再生できない臓器です
そのため今ある腎臓をいかに壊さず、大事に守っていくのかが治療のポイントになってきます
①食事療法
☆猫ちゃんの腎臓病の治療として大きな柱となる1つに『療法食管理』があります
腎臓病用のごはんは“タンパク質”や“リン”などを制限してあり、腎臓への負担を極力減らすごはんです
腎臓病用のごはんを食べている猫ちゃんの方が一般食を食べている猫ちゃんよりも予後が良好という報告もあります!
☆最近ではたくさんのメーカーさんから味や形、香りなどたくさんの工夫を凝らしたごはんがありますので猫ちゃんの好みに合ったごはんを見つけるのも大切です

②飲水量を増やす
☆飲水量を増やすことは腎臓の保護・脱水予防にもつながります
そのためご自宅でのケアとして猫ちゃんになるべく水を飲んでもらうことが大切です!
※常に新鮮なお水を用意する
特に猫ちゃんは新鮮なお水を好むことが多いです☆可能であれが1日数回お水を新しいものに交換する
※様々なタイプのお水を用意してみる
水道水はもちろん湯冷ましのお水、溜めおいたお風呂の水や流れるお水が好きな子もいます
食器や器の材質の工夫や大きさの工夫はもちろん、中にはお水が循環する食器などもありますので試してみるのも1つです

※ウェットフードに変えてみる
ドライフードに比べてウェットフード(缶詰)は水分が多く含まれています なかなかお水を飲んでくれない子はウェットフードに切り替えてみるのもいいでしょう
☆小さいころからウェットフードを食べなれていないと年をとってから、受け入れてくれない猫ちゃんもいます
若い頃からウェットフードをおやつ代わりにあげたり、日頃から慣れさせておくのも大切です

③点滴
腎臓病になると尿をうまく濃縮できずおしっこの量が増え、飲水料だけでは足りず体は脱水してしまいます
自力での食事では体重や水和をうまくできない場合には『皮下点滴』が有効的です
『皮下点滴』とは猫ちゃんの背中の皮膚のたるみに点滴剤を入れ、徐々に吸収させて体の水和を促し脱水を改善させる治療の1つです

④吸着剤や降圧剤などのお薬
体の中に溜まってしまった毒素でもあるリンを吸着するサプリメントの使用
腎臓病の合併症である『腎性高血圧』 血圧の上昇はさらに腎臓へ負担がかかるため血圧を下げるお薬を使う場合があります

※セミントラ
血圧を下げるお薬の1つで、血管を拡張させたり尿へのタンパクの漏れを防ぐ働きがあります

⑤造血ホルモンの投与
腎臓病が進行すると腎臓で作られる造血ホルモンが不足するため、体は貧血してしまいます
それを補うため造血ホルモンを注射することがあります
《最後に…》
近年ではペットフードの質の向上やお薬や治療方法の進化、また猫ちゃんの飼い主様の意識の高さから猫ちゃんの平均寿命は高くなりました
それと同時に腎臓病を抱える猫ちゃんも多くなり、長生きする猫ちゃんたちにとって“ きってもきりはなせない病気” の1つとなっています
普段から猫ちゃんをよく観察し、早期診断・正しい知識をもっての日常のケアが行えれば、猫ちゃんにとって快適で穏やかな生活が送れると考えます
特に猫ちゃんは症状を隠すのが上手な生き物ですので、定期的な健康診断を行うことで、隠れた異常を早期に発見することが猫ちゃんの長生きと健康にもつながります(^^)

今や猫ちゃんもわんちゃんもペットというよりは大切な家族の一員です
そんな家族が1日でも長く、穏やかな日々がおくれるようそら動物病院スタッフ一同全力を尽くします
どんな些細なことでも構いませんので、なんでもご相談ください(^^)

